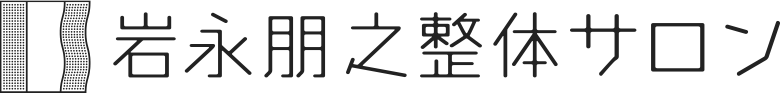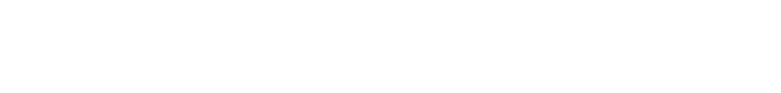子供の姿勢(猫背)

Contents
そもそもいい姿勢とは?
よく姿勢矯正のビフォーアフターのアフター写真で以下のような写真を見かけます。

この姿勢をいい姿勢と捉えてしまうと非常に危険です。
力学的に質量中心(重さの中心)もずれていますし
そして何より交感神経優位の状態です。(興奮状態)
何か面接など緊張すべき場所ではこれでいいでしょう。
しかし、これに近い常にピンッとした状態を常に求めると
お子さんは疲弊してしまい
さらには攻撃的で常にイライラした状態になってしまうでしょう。
またこの状態で固定化してしまい他の動きに問題が起こるかもしれません。
姿勢は理想の位置に勝手におさまります
本来姿勢というのはその時の状況に合わせたベストな状態が勝手に決まります。
自律神経の話が出てきましたが
交感神経優位の時にはそれらに反応する筋肉にスイッチが入ります。
逆に副交感神経優位の時にはそれらの筋肉はオフになります。
それを意識的に変えるのは色々な問題が起こってきます。
緩みたいときに緩めなくなるので睡眠の質などにも影響が出てしまいます。
状況に応じて適切な姿勢になるのがベストです。
固定化しないようにしないといけない
ただし、以下のような写真がいいというわけではありません。

いいというわけではありませんが、悪いわけでもありません。
どんな姿勢もとれる状態がベストであり
そして、静止画でこれがいいとか悪いを判断はできません。
胸を張ったシャキッとした姿勢も取れるし、力を抜いたまるまった姿勢もとれる。
つまり動きのある状態、そしてお子さんが楽そうでイキイキしている状態が本来の良い状態です。
姿勢の状態のチェック方法
抱っこする
抱っこできる大きさの子供であれば抱っこしてあげてください。その時に背中は無理なく丸くなってコンパクトに抱っこできていますか?
逆に背骨に硬さを感じませんか?
でんぐり返りをする
でんぐり返りは綺麗に丸まれていますか?背骨が棒のように硬くなってでんぐり返りが崩れていませんか?
これらができていないと緩むことができていない可能性が高く
背骨も固定化されてきている可能性があります。
歪みを起こす原因
- 習慣(環境)
- 内臓
- 自律神経
- 感覚器の異常
- 発達の問題
習慣(環境)
ゲームを長時間している、いつも歪んだ椅子に座っている、同じ方向のTVを見ている、足のつかない椅子で食事をしている、お父さんやお母さんの姿勢が悪いetc
これらの環境は姿勢を良くない状態で固定化してしまう要因です。
これらを改善しないといくら矯正しても姿勢は戻ってしまいます。
内臓
内臓の状態が悪いと歪みが起こります。これは病気と呼ばれるレベルでなくても起こります。例えば常にお腹が痛い状態が続いているとどうでしょうか?
自然と前屈みの姿勢になると思います。そのような状態が固定化されてしまうと歪みになります。
自律神経
学校や塾そしてご自宅でも常に緊張状態にあったり逆にスイッチが入っていない状態だと自然に姿勢は崩れてしまいます。そこを無視して姿勢だけを指摘することは危険です。
感覚器の異常
最も見逃される原因の一つです。人間は主に視覚、前庭覚、体性感覚と呼ばれる感覚器でバランスをとっています。
実はお子さんは目の見え方が違っていたり前庭感覚が弱かったりすることで姿勢の崩れが起こっていることがあります。
よくこける
乗り物よいしやすいなどがあれば注意が必要です。
またかみ合わせや呼吸の状態でも姿勢の崩れが起こります。
発達発育
発育の過程で感覚器を養っていきます。例えば寝返りやハイハイ、そして日々の遊びの中で感覚器を発達させていきます。
その動きが少なかったり遊ぶ時間が短かったり元々弱いと状況に合わせた姿勢を取ることが難しくなります。
赤ちゃんの時に統合されるべき原始反射が残存していてそれらが姿勢決定に影響を与えていることもあります。
逆に時期に合わない激しい運動などで骨格の形成にエラーが起こっている場合もあります。
子供の姿勢の改善の仕方
当院では静止画の姿勢の良し悪しは参考程度にしかしません。
チェックポイントは
このような流れで猫背を改善していきます。
姿勢が崩れてる子は何かしらの緊張があります。
そのしんどさに本人が気づいている場合もあるし気づいていない場合もあります。
まずはそれらに気づいてあげ楽にしてあげることが重要です。
心身のバランスが取れて動きが出ていれば
「必要な時に必要な姿勢がとれる状態になります」
姿勢を改善される目的での激しいトレーニングや
姿勢矯正ベルトなどは全く無意味と言って良いでしょう。
むしろ子供を苦しめる行為だと理解してください。
またグイグイストレッチしたり無理やり姿勢を取らせるような施術は一次的に改善したように見えますが必ずと言っていいほど後戻りするでしょう。
歯列矯正を受けられている方は一緒に姿勢の矯正を受けられることをお勧めします
最近では歯科医院からのご紹介も増えてきました。
歯科でも姿勢と咬合の関係性が指摘されています。
歯列を無理やり矯正しても姿勢が改善していなければ余計にバランスが崩れ
感覚入力が変わり自律神経の乱れを起こす可能性も考えられます。
歯科医院選びも慎重になられることをお勧めいたします。
歯科の他、メガネなどのツール選びも非常に重要です。
ご希望の場合は各機関をご紹介いたしますのでご相談ください。
どれぐらいの期間で改善するのか?
環境やその子の発育状況によって大きく変わります。
順調にいくと1〜2回の施術でも変化は感じられると思いますが安定しご本人の力で状況に応じた正しい姿勢を取れるようになるまで施術を受けられることをお勧めしています。
当サロンでは12回/1クールを目安に施術しています。
安定してくるとその後は成長のポイントごとにチェックし調整することをお勧めしています。
姿勢の崩れはお子さんの体からのメッセージです。
そのメッセージに耳を傾けてあげてください。
見た目の問題だけでなく頭痛、肩こり、吐き気、その他自律神経の問題を訴えられることもよくあります。
それらの問題が出ている場合はすぐにでも連れてきてあげてください。
小児整体・小児ばり